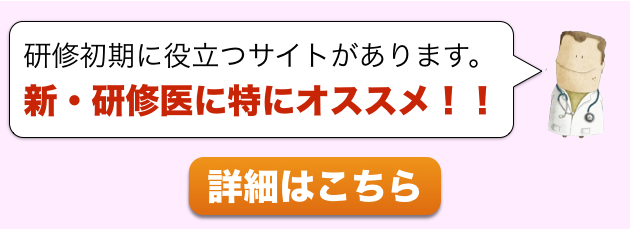肝疾患と栄養
●肝臓が悪くなってしまった人(主に肝硬変)のための食事療法
についてお話します。
肝臓の働き(食べ物を分解・代謝・解毒)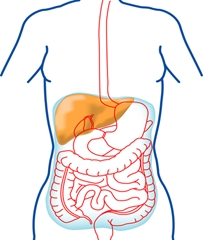
肝臓は、様々な物質の代謝・解毒作用を持っています。
| 糖 | 糖分の貯留と放出を調節 |
| 蛋白 | アルブミン,血液の凝固蛋白など 合成アンモニアの代謝 |
| 脂肪 | コレステロールの代謝,脂肪酸の代謝 |
| ビリルビン | 壊れた赤血球からビリルビン合成 |
肝硬変患者さんでは、これらの機能が落ちてきます。
具体的にどのような点に注意するかまとめますので、肝硬変の患者さんに対して
このような点に気をつけて下さい。
肝硬変症となった人の食事注意点(2つの注意点)
肝硬変とは
「肝臓に線維が多くなり、正常な機能を果たせなくなる状態」です。
正常な機能が果たせなくなるため、
肝臓で処理しなければいけない毒素がたまり、肝性脳症となります。
注意点としては、大きく2点
①肝性脳症の予防をする
②浮腫対策に塩分・水分を制限する
ことが必要になります。
②の浮腫は膠質浸透圧を作るアルブミンの低下により、間質に体液が貯まります。
そのため、肝硬変患者さんでは
塩分制限を行います。場合により水分制限を行うことがあります。
肝性脳症が出やすくなる要素と食事での対策
肝性脳症が起こりやすくなる時として
・便秘
・高たんぱく食を食べた後
・消化管出血
・有効循環血漿量減少(体液量の減少)
・低カリウム血症
・代謝性アルカローシス
などが知られています。
食事として対策できるものは、このうち便通・タンパク制限があります。
モニタリングするべきものとして、カリウムや血液ガスなどがあります。
(利尿剤により低カリウム血症・代謝性アルカローシスが起こるため)
■便通を良くする
食物繊維を多くとり、排便を最低でも1日1回は出せるようにしましょう。
歩行も励行したり(栄養ではないですが、排便のために一緒に意識すると良いです)
場合により下剤、合成2糖類(ラクツロース,ラクチトール)での調整も必要となります。
■タンパク質を制限する
脳症時には 0.6g/kg,治まったら1g/kg等の、タンパク制限が推奨されています。
特に肉食は脳症を誘発しやすい食事となります。
分枝鎖アミノ酸製剤を使用していく場合もあります。
ただし、十分量のカロリーは摂取
late evening meal
また、まだエビデンスが確立しているわけではありませんが
Late evening mealという考え方があります。
肝臓は、糖分を蓄える貯留倉庫ですが、肝硬変となると、この貯留倉庫の中身が空になりやすくなります。
これをグリコーゲンの枯渇と言います。
約6時間、空腹状態になっただけで、貯蔵が空っぽになってしまい筋肉や脂肪を分解してエネルギーを作るようになります。
筋肉を代謝することで、タンパク質を分解するため、そこから毒素(主にアンモニア)が体に増えてしまい肝性脳症を悪化させることがあります。
それを予防するために、夜間の炭水化物の補給を行い
おにぎり、お茶漬け、クラッカー、パンなどを補給する、という方法が
Late evening mealという方法になります。
これは現時点で必ずしも推奨されているわけではないですが
6時間以上の栄養の枯渇で、肝性脳症は悪化しうるというのは覚えておいたほうが良い項目です。
まとめ
肝硬変の場合は便通を良くするよう補助してあげることで肝性脳症に対し注意出来るように
栄養管理が全身の状態にとても役立つ疾患です。
また、体液量は貯留しやすい一方、体液量が減少すると肝性脳症は悪化してしまうため
注意点の多い難しい病態です。
栄養のこともしっかり考えてあげ、良い栄養管理をしてあげましょう。
短期間で要点をつかみたい時
さっと読める肝性脳症患者さんを受け持った時の本としては、内科レジデントの鉄則という本の、肝性脳症の項目内が、数ページでコンパクトにまとまっていて短期間で要点をつかむのには、とても読みやすいです。
研修医的には必携の本なので、周りの誰かはきっと持ってます。聞いてみて、誰かに借りてもよいので目を通してみましょう。
(栄養士さんや看護師さん、薬剤師さんにも読みやすいと思います)