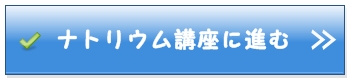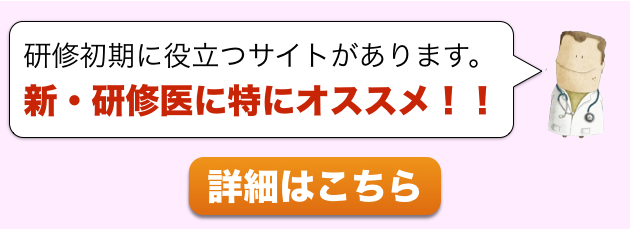体液量は体重の何%か
体液量は体重の何%かは
・水電解質異常での計算の概略に役立つ
・どんな患者さん群で注意するべきかが分かる
という点で、とても重要です。
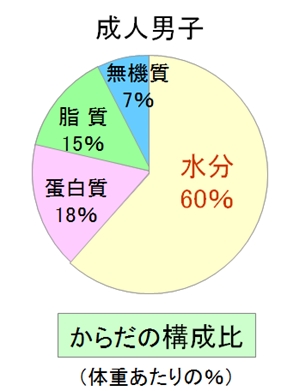
上記は、大体の体液量(体の中の組成)のイメージ図です。
体重の約60%くらいが水分となります。
ただ、この量は小児~成人~高齢者と進むにつれて水分の量が減ってきます。
小児、成人、高齢者の体液量の割合図
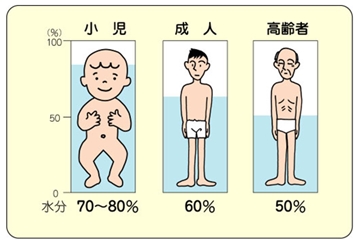
この情報が、臨床的に役立つ場面としては、
特に高齢者に点滴をする時に重要となってきます
同じ3Lの輸液をするにあたって、60kgの成人と高齢者を比較します。
・36Lが体液量の人にとって、8%くらいの量です。
・30Lが体液量の人にとっては、15%もの量になります。
成人と同じくらいのイメージで輸液を行ってしまうと
高齢者は心臓の機能も落ちているので、輸液が多すぎることになり
むくみが出たり、肺水腫となってしまうというリスクがあります。
また、小児で体重が減っている場合、思っているよりも体液量は減っている可能性があります。
こういったことに「意識がめぐるよう」になるので、体液量の組成はとても重要です。
計算のための体液量の割合
私は、低ナトリウム血症や高ナトリウム血症や、普段の輸液でもそうですが、
edelmanの公式を利用しています。(実際にはこれをアレンジして使いやすいように使ってるんですが)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19864338
「Na+]=α?(eNa++eK+)/TBW
という式です。
簡単に言うと、TBWというのがTotal body waterの略で、「総体液量」に当たります。
体重当たりの水分量という意味で、これを計算に使います。
基本的には体液量は体重の何%に当たるかは、下記で計算します。
成人男性:体重×0.6 (体重の60%が水分と考える)
成人女性:体重×0.5
高齢男性:体重×0.55
高齢女性:体重×0.45
となります。
ですが、ちょっとここで考えてみていただきたいことがあります。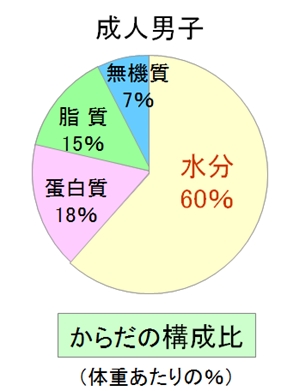
これが体液量の組成なのですが、例えば体重が普段60kgの人が、水分が取れず54kgまで減少したとします。
これは、6kgの水分が失われ、筋肉とか脂肪の成分はあまり変わっていないはずですよね。
そういう方に、じゃあ60%の水分が適切か、という点です。
この場合、約50%くらいが水分になりますよね?
ということで、この割合というのは、その人の有効循環血漿量が少ないときは、ある程度少なく見積もって上げたほうが正確なことがあります。
高Na血症のときは、この係数(体重×係数=TBW)が低めになります。大体40%くらいに見積もると良いでしょう。
(参考図書:腎臓病診療に自身が付く本のの126ページ)はそれくらいにしていました。
私も実際それくらいにしています。
計算式の使い方は、輸液や低ナトリウムの他の項目でも扱っています。
このページでは
・水電解質異常での計算の概略に役立つ
・どんな患者さん群で注意するべきかが分かる
が達成できていれば、とても嬉しいです^^
合わせて読みたい関連記事
ナトリウムの公式
体液量を学んだうえで、ナトリウムの公式を見てみましょう。
ナトリウムと水分の考え方-分数で学ぶ低ナトリウム血症-
ナトリウム濃度は、分数として考えることができます。その見方で体液量を再度捉えなおしましょう。
Edelmanの公式と、ナトリウムの公式の数学的な証明(解説)
上記のナトリウムの公式の証明です。数学が嫌いでない方は是非!